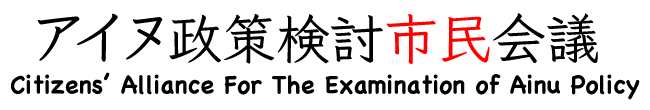アイヌの声をもっと!国会に!「5.15アイヌ施策推進法の“作り直し”を求める院内集会」報告会

日時 2024年8月4日(日)14:30-17:00
会場 かでる2・7(1030会議室)
札幌市中央区北2条西7丁目 道民活動センタービル
参加費 500円
主催 アイヌ政策検討市民会議
【プログラム】
1 ジェフ・ゲーマン代表あいさつ
2 国会院内集会(5月15日、東京)報告
ゲスト報告者
木村二三夫さん/宇佐照代さん/沖津翼さん/原島則夫さん(少数民族懇談会)
市民会議報告者
小坂洋右さん
3 ディスカッション「アイヌの声をもっと!国会に!」
アイヌ政策検討市民会議会員(年会費1000円)は、この集会に無料でご参加いただけます。
アイヌの声を国会に! アイヌ施策推進法の「作り直し」を求める国会院内集会@東京

日時 2024年5月15日(水)13:30~15:00
会場 衆議院第一議員会館・第5会議室
主催 アイヌ政策検討市民会議
協力 少数民族懇談会
入場無料・要申し込み
アイヌ施策推進法は、2019年の施行から5年がたち、見直しの時期を迎えています(同法附則第9条)。私たちアイヌ政策検討市民会議は、これまで重ねてきた議論や、北海道内外のアイヌ団体へのアンケート調査の結果をふまえ、各政党と協働しながら、法律の「作り直し」を求めています。私たちが政府に求めるアイヌ施策とは何か、広く市民のみなさまと共有する集会を国会内で開きます。
アイヌ施策推進法見直しに向けて(提言)
「アイヌの人々の誇りが尊重される社会を実現するための施策の推進に関する法律」(アイヌ施策推進法、2019)の施行から5年後に当たる2024年5月の法律見直しに向けて、アイヌ政策検討市民会議はこのほど修正提言をまとめ、2024年4月20日、札幌で開いた「アイヌの声を国会に! アイヌ施策推進法の“作り直し”を求める集会」で公表しました。
保管するアイヌ民族の遺骨返還における北海道博物館の方針に再考を求めます(声明)
2023年10月4日
北海道知事 鈴木直道 様
北海道博物館館長 石森秀三 様
環境生活部長 加納孝之 様
わたしたちアイヌ政策検討市民会議は、日本の先住民族であるアイヌ民族に対する諸政策の課題・問題点を広く社会に訴え、共有していこうと、アイヌ民族と市民が組織した団体です。アイヌ政策を、国や北海道主導のものから当事者アイヌの自決権に基づくものへと転換することを大きな目的に掲げて活動しています。このたび、北海道博物館が保管するアイヌ民族の遺骨を、受け入れ先が現れない場合に国立アイヌ民族博物館(ウポポイ)へと集約する方針を示したことに懸念を覚え、再考を求めます。
北大教授差別発言への要望書
2023年2月10日
北海道大学総長 寳金清博 様
北海道大学アイヌ共生推進本部長 山本文彦 様
貴大学総長名で公表された一文「本学教員による不適切なSNS投稿について」(2022年1月20日づけ)に、この投稿による直接的な被害者はもとより、市民社会は大きなショックを受けています。貴大学教授(しかも貴大学の部局執行部にある教授)が〈先住民族であるアイヌ民族をはじめとする民族的マイノリティに関する不適切な発言や、排外主義的な発言を繰り返していた〉事実に呆然とさせられただけではありません。貴大学が〈ダイバーシティ・インクルージョン推進本部、アイヌ共生推進本部を設置し、差別や偏見を乗り越えたバイアスフリーキャンパスを実現するため、本学所属の教員・職員・学生に対する啓発プログラムも推進〉していたにもかかわらず、もっとも高い倫理観を期待される立場の教授がヘイトスピーチに走るのを予防できなかったことに、失望と反発が広がっているのです。
自衛隊のマークにアイヌの伝統文様が使われることについて憂慮します(要請文)(2023/01/16)
わたしたちアイヌ政策検討市民会議は、日本のアイヌ政策の問題点を広く市民社会で共有し、国や道主導のアイヌ政策から当事者アイヌの自己決定権に基づくアイヌ政策へと転換するための基盤、すなわち代替策をつくり、日本政府や国連の人権監視機関など国内外の関係諸機関に提示することを目的に活動しています。わたしたちは、航空自衛隊第二航空団空団マークにアイヌ文様が「使われている」ことについて憂慮します。
杉田水脈総務大臣政務官のヘイトスピーチに抗議し、更迭を求めます(2022/12/08)
アイヌ民族も含めて、さまざまなマイノリティを貶め、攻撃する杉田政務官のヘイトスピーチと、それを容認・拡散し続ける政府のふるまいを、わたしたちは看過できません。このまま杉田氏を留任させておくことは、岸田文雄内閣がマイノリティを差別する政権であることを内外に示すことになると、わたしたちは憂慮しています。杉田氏に強く抗議するとともに、杉田氏を政府要職に起用しつづける岸田政権に抗議し、以下の項目について要請します。
- 政府は、杉田水脈総務大臣政務官の行動・発言が人種差別にあたることを確認してください。
- 政府は、杉田水脈総務大臣政務官の行動・発言が人種差別にあたることを本人自身に明確に認識させてください。
- 政府は、杉田水脈総務大臣政務官がヘイトスピーチの広範な被害者に対して直接謝罪する場を設定してください。
- 政府は、杉田水脈総務大臣政務官をただちに罷免してください。

新着資料(2022/10/19)
「歴史をねじ曲げて今、アイヌ民族政策が作られようとしている!
2017年2月18日 北海道大学アイヌ・先住民研究センター落合研一准教授の講演に抗議する集会報告集」
発行者 教科書のアイヌ民族記述を考える会
発行日 2017年6月8日
表紙のアイヌ文様 光野智子「カムイピリマ 」― 神がそっと教えてくれる ―
表紙デザイン 佐々木洋子
声明 選挙に紛れ込んだヘイトスピーチを非難します(2022/07/17)
2022年7月10日投開票の第26回参議院議員通常選挙において、一部の政党・候補者が、先住民族アイヌに対するヘイトスピーチの疑いが濃厚な主張を公然と繰り返し、アイヌのアイデンティティを持つ大勢の人々が尊厳を傷つけられました。公職選挙は民主主義の根幹であり、候補者には、自由かつ平等な発言機会が保障されなければなりません。しかし、一部政党・候補者は、その原則をいわば逆手にとって、先住民族アイヌの存在を否定する言葉を選挙公報・街頭演説などによって拡散しました。アイヌ/非アイヌの会員で構成されるわたしたちアイヌ政策検討市民会議は、アイヌの人権を何よりも大切にしたいと考えており、このたびの参議院選挙に乗じた一部政党・候補者のヘイト的な発言を強く非難します。
樺太アイヌの歴史を考える—物語でも、捏造でもなく—

アイヌ政策検討市民会議は、2022年6月26日に札幌市教育文化会館で開いた2022年度定期総会で、丸山博代表の退任を了承し、運営委員のジェフ・ゲーマンさんを新しい代表に選出しました。
ジェフ・ゲーマン代表のあいさつ
北海道大学大学院メディア・コミュニケーション研究院及び教育学院のジェフ・ゲーマンです。きょうをもって、アイヌ政策検討市民会議の代表を仰せつかりました。……続きはこちら

「2024 年『アイヌ施策推進法』改正に向けてのアンケート調査報告書」を公開しました。概要をまとめたプレスリリースも合わせてどうぞ。(2022年3月23日)
2022年3月25日(金)13:30から、札幌市の道政記者クラブ(北海道庁2階)で記者会見を開きました。
冊子印刷版をつくりました。無料でお配りしています。ご活用ください。お申し込みはこちらから
オンライン学習会の録画を公開しました
北海道・南樺太の日本による戸籍制実施と先住民族アイヌ
講師 遠藤正敬さん
とき 2021年10月9日(土曜)14:00-15:30
ZOOM会議システムによるオンライン開催
主 催 アイヌ政策検討市民会議
協 力 樺太アイヌ(エンチウ)協会/エンチウ遺族会/さっぽろ自由学校「遊」
差別発言放映の原因究明と再発防止策の徹底を求めます(2021年3月15日)
日本テレビ代表取締役会長執行役員 大久保好男様
STVテレビ代表取締役社長 根岸豊明様
3月12日、貴社の情報番組で放映されたアイヌに対する重大な差別発言は看過できません。しかも、一個人が番組の進行中に突発的に発したものではなく、事前に収録されていた発言を放映した以上、貴社には今回の差別発言のチェックを怠り、放映した責任が厳しく問われます。差別発言に対する真摯な謝罪は大切です。しかし、謝罪だけに矮小化される問題ではありません。なぜ、このようなことが起きたのか、差別発言が差別される側、あるいはネット上の差別する側にどのような影響を与えたのか、さらに今後このような事態を繰り返さないためにはどうすればいいのかといったことなどについて調査し、公共言論空間を形成するメディアとして、今後のあるべき姿を再構築すべきだと考えます。
「北海道アイヌ政策推進方策(素案)」に対する意見書を提出しました(2021年3月2日)
1980年代、北海道は当時の北海道ウタリ協会の「アイヌ民族に関する法律(案)」を受け止め、それをアイヌの人たちと議論して一部修正したものを法律として制定するよう国に働きかけたことがありました。しかるに、今回の北海道アイヌ政策推進方策(素案)は、アイヌ政策の出発点である歴史認識について、日本がアイヌの土地(北海道、千島、樺太)を植民地化し、先住民族アイヌに対して行った数々の不正義についての真摯な反省、謝罪が示されていません。また、世界は2007年に国連で採択された「先住民族の権利に関する国際連合宣言」(以下、国連宣言と略称)の実現に向けて取り組んでいるということも共有されていません。私たちは、国連宣言の実現を求めるアイヌの人びとはもとより、世界中の市民社会と連帯し、先住民族の自己決定、土地や資源などへの権利の回復をグローバルアジェンダ(世界が力を合わせて共通に取り組むべき課題)ととらえ、四つの観点から、北海道のアイヌ政策の転換を求めます。

アイヌ政策検討市民会議年次リポート2019-20「ウポポイについて考えよう」を発行しました
主な内容
Part 1 シンポジウム「ウポポイについて考えよう」
シンポジウムの開催にあたっての問題意識/田澤 守「エンチウからの異議申し立て」/ジェフ・ゲーマン「博物館を5つの視点で語る」/丸山 博「ウポポイとは何か」/清水裕二「79 歳アイヌが見聞きしたウポポイ」/パネル討論(パネリスト:川村久恵・清水裕二・田澤 守・丸山 博・ジェフ・ゲーマン)/シンポジウムの反響から
Part 2 アイヌのサケ漁業権をめぐって
モベツ川事件/浦幌十勝川サケ裁判/「アイヌ(=ひと)の権利をめざす会」共同代表と呼びかけ賛同人のスピーチ:貝澤耕一・萱野志朗・宇梶静江・アト゚イ・鹿田川見・木村二三夫/電子署名サイトに寄せられたコメントから
Part 3 資料
国際連合EMRIPに対する北海道アイヌの声明(2020/11/30)

国際連合・人権高等弁務官事務所(OHCHR)が、2020年12月1日(日本時間午後5時〜)にオンラインで開催する「先住民族の権利に関する専門家機構 Expert Mechanism on the Rights of Indigenous Peoples(EMRIP)」第13回アジア・太平洋地区会合に合わせ、木村二三夫・平取アイヌ遺骨を考える会共同代表が同機構に提出/受理された声明文を掲載します。平取アイヌ遺骨を考える会のほか、「アイヌ(=ひと)の権利をめざす会」「アイヌ政策検討市民会議」「さっぽろ自由学校「遊」」が共同提出者に名前を連ねています。
photo : Hirata Tsuyoshi
「核のごみ」最終処分場の選定をめぐる自治体の決定に関する声明(2020年10月5日)
私たちは、町内外の反対や異論のみならず、北海道を植民地化した歴史を顧みず、先住民族アイヌの国際人権基準も考慮することなく、交付金を目当てにした寿都町および神恵内村の拙速な意思決定は、マイノリティの人権保障という世代内の平等に加えて資源・環境に関する世代間の衡平を求める現代民主主義に反するものとして、強く抗議します。
2020年8月19日、モベツ川でのサケ漁をめぐって、北海道知事に要望書を出しました。
Press Conference : Caranke! Objection to the New Ainu Bill
Ainu continue fight for language and culture in Japan
市民会議からの提案 statements
アイヌ・非アイヌの個人たち、また数々のグループが、市民会議を通じて、「先住民族の権利」やアイヌ政策についての要望・提案・声明を発表しています。